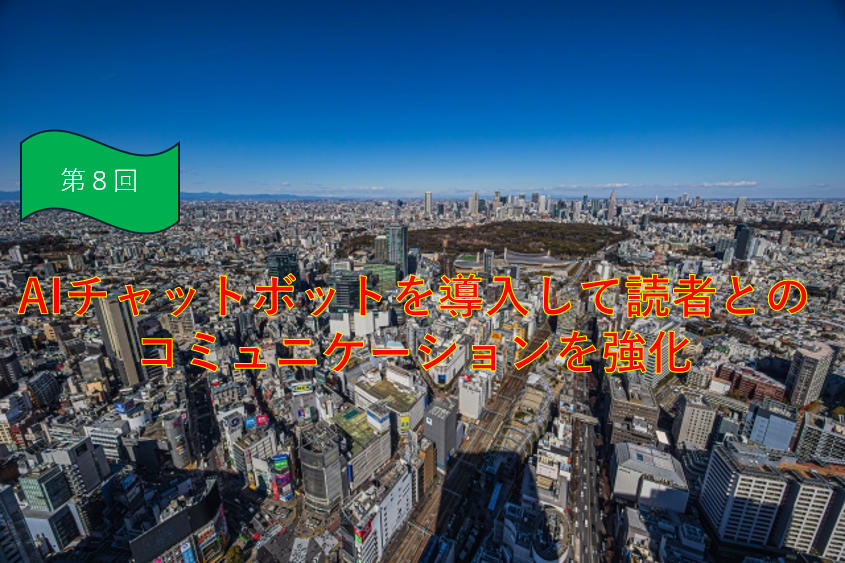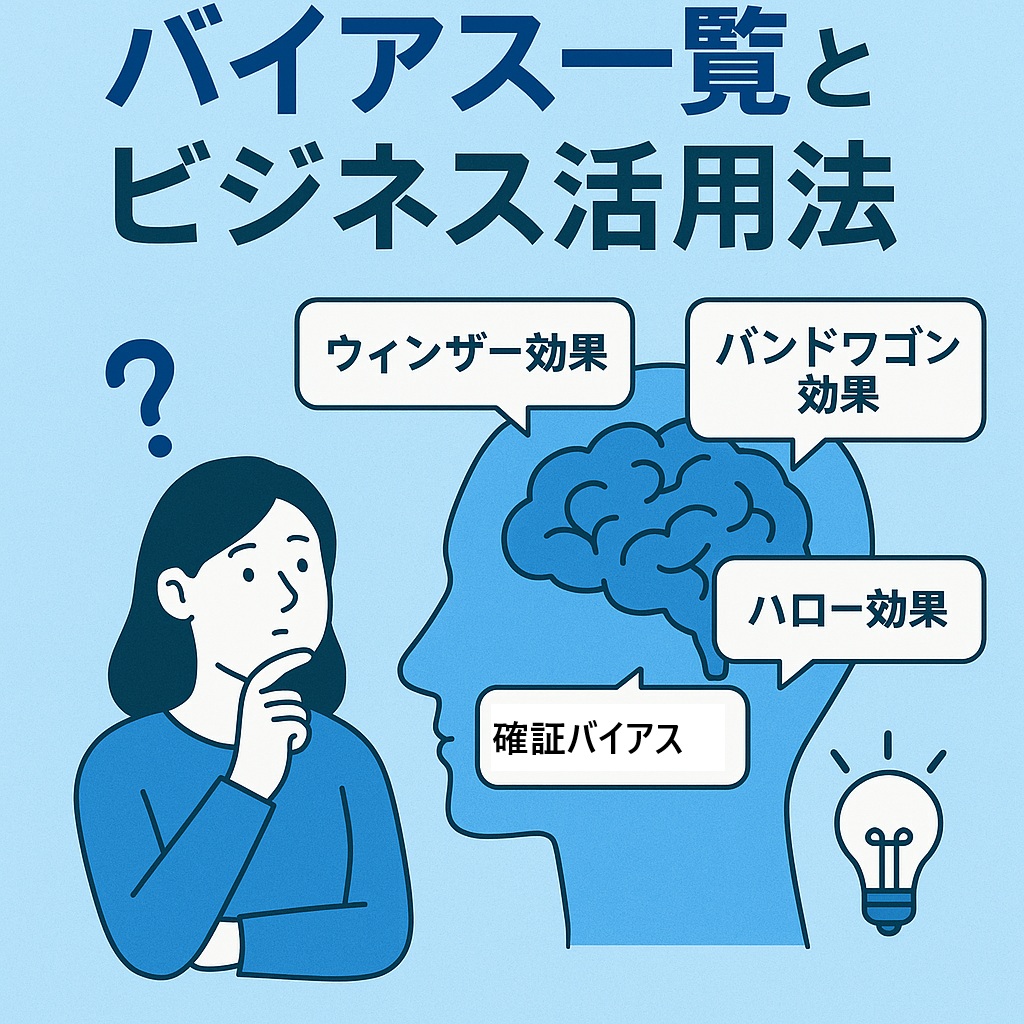こんにちは、斎藤です。
前回に引き続き、ブログを投稿していてこんな悩みを抱えている人は居ますよね。
「記事を書いても検索結果に出てこない…」
「SEOって難しそうで手を付けてない…」
私もその悩みを抱えている一人です。
なので、今日はWordPressでできる基本のSEO対策を10個ご紹介していこうと思います。
目次
- SEOとは?まずは基本をおさえよう
- 1. パーマリンクを「投稿名」にする
- 2. タイトルにキーワードを入れる
- 3. メタディスクリプションを設定
- 4. 見出し(hタグ)を適切に使う
- 5. Alt属性で画像にもSEO対策
- 6. 内部リンクをしっかり設計
- 7. モバイルフレンドリーなデザイン
- 8. 表示速度の改善
- 9. プラグイン「All in One SEO」の活用
- 10. 記事は最低1000文字以上を意識
- まとめ|すべて実践すればSEOの基礎はOK!
SEOとは?まずは基本をおさえよう
最初に、SEOってなんだろうという事からですね。
SEOとは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略になります。
簡単に言うと、Google検索で上位表示させてアクセスを集めるための施策です。

SEOは一朝一夕で成果が出るものではありませんが、正しい方向で継続すれば、半自動的にアクセスが増える「資産」になります。
まずは1記事ずつ、「検索意図に合った内容」「読みやすい構成」「わかりやすい言葉」で書いていくことが大切です。
1. パーマリンクを「投稿名」にする
WordPressの初期設定だとURLが数字だけになりますが、「投稿名」にするとSEO的に有利になります。
パーマリンクを「投稿名」に設定するメリット
WordPressでブログを始めたばかりの方は、まずパーマリンク設定を見直しましょう。
初期状態では「?p=123」のような意味のないURLになっていることが多く、SEOにもユーザー体験にも不利になっています。
✅ そもそもパーマリンクとは?
パーマリンクとは、記事ごとに割り当てられるURLのことです。
例:
https://example.com/?p=123
https://example.com/wordpress-seo-tips(投稿名)
✅ 投稿名にするメリット
- SEOに強くなる:URLにキーワードが含まれることで、Googleに内容が伝わりやすくなります。
- 読者にわかりやすい:SNSなどでURLが共有されたとき、記事内容が一目で分かります。
- 管理しやすい:投稿名ベースのURLは整理しやすく、リンク切れも防げます。
- 後からの編集・リライトがしやすい:URLが意味を持つため、記事の再利用時も困りません。
✅ 投稿名の設定方法(WordPress)
パーマリンクを投稿名にする設定方法は以下になります。
- WordPress管理画面 → 「設定」→「パーマリンク」を開く
- 「投稿名」にチェックを入れる
- 「変更を保存」をクリック

⚠️ 注意点
ただ、ここで注意する必要があります。
- 日本語の投稿名はURLが長くなり読みにくくなるため、英数字に変更するのがベストです。
- 運用中に変更するとリンク切れのリスクがあるため、ブログ開始時に設定するのが理想です。
パーマリンクはブログ全体の信頼性やアクセスにも関わる重要なポイントです。
最初に正しく設定しておくことで、SEOにも大きな効果が期待できます。
2. タイトルにキーワードを入れる
ユーザーが検索しそうなキーワードを、記事タイトルの前半に含めるのがポイントになります。
タイトルにキーワードを入れることのメリット
SEO対策の基本のひとつが、記事タイトルにキーワードを入れることです。
検索エンジンとユーザーの両方にとって重要な要素となります。
✅ 検索順位が上がりやすくなる
Googleは、ページのタイトル(<title>タグ)を重要な評価対象としています。
そのため、検索されたいキーワードをタイトルに含めることで、検索順位が上がりやすくなります。
✅ 検索ユーザーのクリック率(CTR)が向上する
検索結果に表示されたとき、ユーザーは自分の悩みや関心に合ったタイトルをクリックします。
例えば、以下のように違いが出ます:
✖ 悪い例:「ブログ始めました」
◎ 良い例:「【初心者向け】WordPressブログの始め方5ステップ」
具体的なキーワードがあることで、ユーザーの興味を引き、クリックされやすくなります。
✅ SNSやリンクでも伝わりやすい
タイトルは検索だけでなく、SNSや他のブログからリンクされたときにも記事の内容を端的に伝える役割を果たします。
キーワードが入っていれば、拡散力やシェア率にも影響します。
✅ キーワードの入れ方のコツ
- できるだけタイトルの前半に入れる(検索結果では前半が目立つ)
- 自然な文脈で読者の関心を引くようにする
- 無理に詰め込まず、1〜2語に絞るのが効果的
SEOにおいてタイトルの最適化は、最も効果が高く、すぐに実践できる施策のひとつです。
記事を書く前に、検索されたいキーワードを意識してタイトルを決めましょう。
3. メタディスクリプションを設定
検索結果に表示される要約文です。
クリック率(CTR)アップに貢献します。
メタディスクリプションを設定することのメリット
メタディスクリプション(meta description)とは、検索結果に表示される記事の「説明文」のことです。
WordPressでは、SEOプラグイン(例:「All in One SEO」や「Yoast SEO」)を使って簡単に設定できます。
✅ 検索結果で目立ち、クリック率が上がる
ユーザーは検索結果の中から、タイトルとディスクリプションを見て記事を選びます。
内容を魅力的にまとめておくことで、クリック率(CTR)を高める効果があります。
例:
【悪い例】「記事の内容です。」
【良い例】「初心者でもできるSEO対策10選をわかりやすく解説。ブログのアクセスアップに今すぐ役立つ情報を紹介します。」
✅ 記事の内容が明確に伝わる
検索ユーザーにとって、「この記事には何が書かれているのか?」がすぐ分かることはとても重要です。
適切なメタディスクリプションは、読者と記事とのミスマッチを防ぎ、離脱率も下げます。
✅ SNSでシェアされたときの表示にも影響
SNS(例:X(旧Twitter)やFacebook)でシェアされた際、メタディスクリプションが自動表示される場合があります。
そのため、第一印象を決める重要な要素として活用できます。
✅ 書き方のポイント
- 全角80〜120文字程度を目安にする
- 記事の要点・メリット・対象読者を明確に
- キーワードを1〜2語含めると効果的(自然な形で)
✅ WordPressでの設定方法(All in One SEO使用時)
- 投稿編集画面の下部にある「AIOSEO設定」欄へスクロール
- 「メタディスクリプション」欄に文章を入力
- 保存して完了(リアルタイムでプレビュー表示されます)

読者の心をつかむ一文が、記事の価値を何倍にも高めます。
ぜひ毎記事、丁寧にメタディスクリプションを書いてみましょう。
4. 見出し(hタグ)を適切に使う
h2→h3→h4と階層を意識。読みやすさにも直結します。
見出し(hタグ)を適切に使うことのメリット
ブログ記事を書くうえで重要なのが、見出しタグ(hタグ)の使い方です。
見出しは記事の構造を示すだけでなく、SEOと読みやすさの両面で大きな役割を果たします。
✅ 記事の構造が明確になり、SEOに有利
検索エンジン(Googleなど)は、hタグを使ってページ内の情報の階層や内容の優先度を理解します。
適切に見出しを設定することで、検索エンジンにページのテーマが伝わりやすくなり、SEO評価が上がる可能性があります。
✅ 読者が読みやすくなる(離脱率低下)
長文でも見出しがしっかり使われていれば、読者は必要な情報にすばやくアクセスできます。
特にスマホ閲覧では、「見出しのスキャン読み」が多いため、しっかりした構成が読了率に直結します。
✅ 見出しの正しい使い方(基本ルール)
- h1タグ:記事タイトルに1回だけ使う(自動で設定されることが多い)
- h2タグ:大見出し(主要セクション)
- h3タグ:h2の中の小見出し(補足や細分化)
- h4〜h6:必要に応じて階層を深くできるが、基本はh2・h3で十分
✅ 良い例と悪い例
✖ 悪い例:
<h2>まとめ</h2>
<p>ここまでありがとうございました。</p>(途中の見出しがまったくない)◎ 良い例:
<h2>ブログ初心者がアクセスを集めるコツ</h2>
<h3>キーワード選定の基本</h3>
<h3>記事構成の型を覚える</h3>
✅ WordPressでの設定方法
- 記事編集画面で、見出しにしたいテキストを選択
- 「段落」→「見出し」→「h2」や「h3」などを選ぶ
- 読みやすい順序で階層を整理する
 見出しはSEOと読者満足度を両立させるカギです。
見出しはSEOと読者満足度を両立させるカギです。
読みやすく、分かりやすい記事構成を目指して、見出しの使い方にも意識を向けましょう。
5. Alt属性で画像にもSEO対策
画像に説明テキスト(alt)を入れることで、Google画像検索でも表示されやすくなります。
Alt属性で画像にもSEO対策することのメリット
画像を使うと記事が視覚的にわかりやすくなりますが、画像だけでは検索エンジンには内容が伝わりません。
そこで重要なのがAlt属性(代替テキスト)の活用です。
SEOにおいても、ユーザーにとっても多くのメリットがあります。
✅ 検索エンジンに画像の内容を伝えられる
Googleなどの検索エンジンは、画像の内容そのものを完全には読み取れません。
しかし、Alt属性にキーワードを含めた説明文を設定することで、検索エンジンに画像の意味を伝えられ、画像検索にもヒットしやすくなります。
✅ アクセシビリティが向上する
視覚障がいのあるユーザーや、画像の読み込みに失敗したユーザーにとって、Alt属性は画像の代わりに内容を伝える重要な要素です。
これにより、誰にとっても読みやすいサイト(ユーザビリティの高いサイト)を構築できます。
✅ ペナルティ回避とSEO品質向上
Alt属性が空白または無意味なものばかりだと、Googleの評価が下がる可能性があります。
正しいAltの活用は、ページ全体のSEO品質を底上げする要素となります。
✅ 書き方のポイント
- 画像の内容を簡潔に表現する(冗長にしない)
- キーワードを自然に含める(詰め込みすぎはNG)
- 装飾画像(区切り線など)は
alt=""で空にする
✅ WordPressでAlt属性を設定する方法
- 投稿編集画面で画像をクリック
- 右サイドバーの「代替テキスト」欄に、画像の説明文を入力
- 更新・公開ボタンをクリックして保存
 Alt属性は小さな設定ですが、SEOに大きく貢献する要素です。
Alt属性は小さな設定ですが、SEOに大きく貢献する要素です。
すべての画像に適切なAltテキストを設定し、Googleにもユーザーにも優しい記事を目指しましょう。
6. 内部リンクをしっかり設計
関連する過去記事へのリンクは、SEOにも読者体験にも◎。
内部リンクをしっかり設計することのメリット
ブログ内の記事同士をつなげる内部リンクは、SEOとユーザビリティの両方にとって非常に効果的な施策です。
ただ単につなげるのではなく、「設計して貼る」ことが、ブログ全体の価値を高めます。
✅ SEOの評価を高める
Googleは内部リンクを通じて、どのページが重要かを判断します。
例えば、重要な記事に複数の内部リンクが集まると、その記事の評価が高くなり、検索順位の向上につながります。
✅ 読者の回遊率・滞在時間がアップする
関連性の高い記事同士を内部リンクでつなげることで、読者が他の記事も自然に読んでくれるようになります。
その結果、サイト内の回遊率や滞在時間が伸び、SEOにも良い影響を与えます。
✅ 記事の構造や専門性が伝わる
内部リンクを戦略的に使うことで、「このサイトは体系的に情報を発信している」という印象を与えることができます。
特に専門性が求められるテーマでは、専門知識の信頼性を高める効果も期待できます。
✅ クローラビリティ(Googleの巡回効率)が向上
Googleのロボット(クローラー)は、リンクをたどってページを発見・評価します。
内部リンクが適切に構成されていれば、すべてのページが適切にインデックスされやすくなります。
✅ 内部リンクの貼り方のコツ
- 関連性のある記事同士をつなぐ
- アンカーテキストに記事内容を表す自然なキーワードを含める
- 1記事あたり2〜3本を目安に配置(多すぎ注意)
- カテゴリーやタグとの連携も意識する
✅ WordPressで内部リンクを設定する方法
- 記事編集画面でリンクを挿入したいテキストを選択
- ツールバーの「リンク」ボタンをクリック
- 内部記事のURLまたは記事タイトルを検索して選択
- 「適用」または「Enterキー」で確定

内部リンクは、「読者にも検索エンジンにも親切なナビゲーション」です。
1記事ずつ丁寧に設計することで、ブログ全体のSEO力と信頼性が高まります。
7. モバイルフレンドリーなデザイン
スマホ表示に最適化されていないと、順位が落ちることも。
モバイルフレンドリーなデザインにすることのメリット
スマートフォンでの閲覧が主流となった今、モバイルフレンドリーなデザインは、ブログ運営において欠かせない要素です。
単に「スマホでも見れる」だけでなく、ユーザーと検索エンジンの両方にメリットがあります。
✅ Googleの検索順位に好影響を与える(モバイルファーストインデックス)
Googleは現在、モバイル版ページを優先して評価(モバイルファーストインデックス)しています。
スマホで見にくいサイトは評価が下がる恐れがあるため、モバイル対応はSEO対策の基本です。
✅ スマホユーザーの離脱を防げる
モバイル非対応のサイトは、表示が崩れたり文字が小さくなったりして、読みにくさによる離脱率の上昇につながります。
モバイルフレンドリーなレイアウトは、ユーザー体験(UX)を大幅に改善します。
✅ SNS経由のアクセスにも強い
SNSからの流入はほとんどがスマートフォン経由です。
そのため、スマホで見づらいブログはSNSでシェアされても読まれない可能性が高くなります。
✅ デザインとコンバージョン率の向上
モバイル対応によってボタンやCTAのタップしやすさが改善され、クリック率や成果率(CVR)もアップします。
ブログでの収益化を目指すなら、スマホ対応は必須の施策です。
✅ モバイルフレンドリーデザインのチェックポイント
- 文字サイズがスマホで読みやすいか
- 画像や表が画面幅に合わせて表示されるか
- ボタンやリンクがタップしやすい位置にあるか
- 余白や行間が詰まりすぎていないか
✅ WordPressでモバイル対応する方法
- レスポンシブ対応のテーマを選ぶ(例:Cocoon、SWELLなど)
- カスタマイズ画面でスマホ表示を確認しながら調整
- GoogleChromeの拡張機能「Lighthouse」でチェック
今やブログ訪問者の7〜8割がスマホユーザーとも言われています。
すべての読者にストレスなく読んでもらうために、モバイル対応は最優先で取り組むべきSEO施策です。
8. 表示速度の改善
画像を圧縮したり、キャッシュ系プラグインを導入すると改善されます。
表示速度を改善することのメリット
サイトの表示速度は、SEOにもユーザー満足度にも大きな影響を与える要素です。
特にスマートフォンユーザーの増加により、「すぐに表示されるサイト」が求められています。
✅ SEO評価が向上する(Core Web Vitalsにも影響)
Googleはサイトの読み込み速度をランキング要因として評価しています。
特に2021年以降導入された「Core Web Vitals」では、表示速度(LCP)・応答性・レイアウトの安定性が重視されています。
✅ 離脱率が減少する
ページが表示されるまでに3秒以上かかると、半数以上のユーザーが離脱するという調査結果もあります。
表示速度を改善すれば、読者が記事を読む前に離脱するリスクを大幅に減らせます。
✅ ユーザー体験(UX)の向上
読み込みが速いページは、読者にストレスを与えません。
ページ遷移もスムーズになり、回遊率や滞在時間の向上にもつながります。
✅ 広告収益やコンバージョン率にも好影響
表示速度が速いサイトでは、広告が正しく表示されやすく、クリック率やコンバージョン率も向上します。
Google AdSenseなどを利用している場合は、表示速度が収益に直結する可能性があります。
✅ 表示速度改善のための主な方法
- 画像の最適化(WebP形式やサイズ圧縮)
- 不要なプラグインの削除
- キャッシュプラグインの導入(例:WP Fastest Cache、LiteSpeed Cache)
- 高速なサーバーを選ぶ(国内向けならConoHa WINGなど)
- CDNの活用(Cloudflareなど)
✅ 表示速度のチェック方法
- Google PageSpeed Insights にアクセス
- 自分のブログURLを入力して分析
- 「パフォーマンス」スコアと改善ポイントを確認
「表示速度=ユーザー満足度」と言っても過言ではありません。
WordPressの設定を見直して、快適なサイト環境を目指しましょう。
9. プラグイン「All in One SEO」の活用
WordPress初心者の強い味方!メタ情報やサイトマップも自動で設定できます。
All in One SEOを活用することのメリット
All in One SEO(AIOSEO)は、WordPress初心者から中級者まで幅広く使われているSEO対策用プラグインです。
難しい知識がなくても、検索エンジンに強いサイトを作れるのが魅力です。
✅ メタタイトル・メタディスクリプションの設定が簡単
各記事ごとに検索結果に表示されるタイトルや説明文(メタ情報)を自由に設定できます。
クリック率(CTR)の向上に直結し、SEO効果を高められます。
✅ サイトマップの自動生成
Googleにサイト構造を伝えるためのXMLサイトマップを自動で作成・更新してくれます。
検索エンジンのインデックス速度が向上し、最新の記事もすぐに評価されやすくなります。
✅ SNS連携によるOGP設定が簡単
X(旧Twitter)やFacebookなどで記事がシェアされた際のタイトル・画像・説明文を事前に指定できます。
これにより、SNS上での見栄えが良くなり、シェア効果がアップします。
✅ SEOチェックと分析機能
記事のSEOスコアや、改善すべき項目(タイトルの長さ、キーワード使用状況など)をリアルタイムで診断してくれます。
SEO初心者でも何を直せばいいかが一目瞭然です。
✅ パンくずリストやローカルSEOの設定も対応
Googleに伝える構造化データ(schema.org)対応のパンくずリストや、店舗情報を扱うブログに便利なローカルSEO機能なども搭載されています。
✅ All in One SEOの基本設定ステップ
- WordPress管理画面 → 「プラグイン」→「新規追加」
- 「All in One SEO」を検索してインストール・有効化
- 「AIOSEO」メニューから基本設定を進める
- 投稿ごとにタイトル・ディスクリプションなどを入力
All in One SEOは、SEO対策を効率化しながら検索上位を狙える強力なサポーターです。
「とりあえず入れておいて損はない」プラグインのひとつです。
10. 記事は最低1000文字以上を意識
Googleは情報量が豊富で網羅的なページを評価します。目安は1000〜1500文字以上。
記事は最低1000文字以上を意識することのメリット
ブログを書く際、記事の文字数はSEOにもユーザー満足度にも大きな影響を与えます。
特に1000文字以上を目安にすることで、検索エンジンと読者の両方に良い印象を与えることができます。
✅ Googleが「有益なコンテンツ」と評価しやすくなる
Googleはユーザーにとって価値のあるコンテンツを評価します。
極端に短い記事は情報量が少なく、「薄いコンテンツ」と判断されて検索順位が上がりにくくなります。
一方で1000文字以上あると、ある程度の深掘りができるため、評価されやすくなります。
✅ 読者が「読む価値がある」と感じやすい
文字数が少なすぎると、知りたい情報が十分に得られないと感じられ、読者の満足度が下がる可能性があります。
1000文字以上のボリュームがあれば、読者の疑問を丁寧に解消できる記事になりやすくなります。
✅ 滞在時間が長くなり、SEOにもプラス
記事の文字数が多いほど、読者がページに滞在する時間も長くなります。
Googleは滞在時間も間接的に評価基準として見ており、SEO効果が期待できます。
✅ 関連キーワードも自然に含めやすくなる
長めの記事では、メインキーワードに加えてサブキーワードや関連語も自然に盛り込めるため、ロングテールSEOにも効果的です。
✅ 書く時のコツ
- 導入・問題提起 → 解決策 → まとめ という構成を意識する
- 見出し(h2, h3など)で構成を整理し、読みやすい文章にする
- 例や具体的な体験談を加えることで、文字数を自然に増やす
✅ ただし「文字数=質」ではない
あくまで大切なのは読者にとっての有益性です。
文字数を増やすことに固執しすぎず、無駄なく、丁寧に情報を伝えることを意識しましょう。
「最低1000文字」はあくまで目安ですが、初心者にとっては良いガイドラインになります。
読者満足とSEOを両立するためにも、丁寧な記事作りを心がけましょう。
すべて実践すればSEOの基礎はOK!
- まずは設定・記事構成など、基本を押さえることが大切
- 読者のためになる記事を書くことが、結果的にSEOにつながる
- 次は「アクセス分析」や「SNS集客」へとステップアップしよう!
今回は、WordPress SEO対策10選について記載してきました。
少しでもみなさんのお役に立てたなら幸いです。
ここまで読んで下さりありがとうございます。
それではまた次回!